【修了公演演出家インタビュー】佐々木透[劇作家・演出家/リクウズルーム主宰]
こんにちは、広報アシスタントの川島です。
今回は俳優養成講座修了公演の作・演出を担当される、佐々木透さんにお話をうかがってまいりました!

2001年より、ク・ナウカシアターカンパニーで演出家・宮城聰(現・SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術監督)のもと俳優として活動し、2007年、ソロユニット「リクウズルーム」を開始。青年団演出部を経て、戯曲のほか、現代詩手帖に詩を発表するなど、幅広い文筆活動を展開されています。
戯曲の限界を探ることをテーマに、見る者に新たな視点を与える演劇を創り続けている佐々木さん。修了公演はどんな作品になるのでしょうか?
佐々木さんご自身のことから修了公演の構想まで聞いてまいりました!
それではどうぞ!
******************************************************************************************************
―まず、演劇の世界に飛び込まれたきっかけは?
佐々木 元々「言葉」に関することをやりたくて。「言葉」なら何でも良かったんですけど、最初は語学のことなどを考えていたりしたのですがそっちの方には行かず、あれよあれよと演劇の方に流れて来てしまいました(笑)。
―ク・ナウカ シアターカンパニーに入る前も演劇はやられていたんですか?
佐々木 演劇をやりたかったんですけど、高校に演劇部がなくて出来なかったんです。同好会みたいなのはあったんだけど、二人くらいしかいなかった(笑)。それでどこかで勉強するところはないかなと思って、地元で演技とかナレーションなどを教えるところで色々話を聞いたら「本格的に演技の勉強をしたいんだったら東京じゃないとダメだよ」というようなことを言われて、それで東京に来ました。
上京直後は知り合った連中でいわゆる小劇場演劇みたいなのをやっていたんですけど、まぁ…演劇の世界は、とにかくお金にならない。お金が入って来ないだけならまだしも出て行くだけで、しかも生活費以外で出て行くから「このサイクルに何の未来があるんだろうな」って思って。それで10代に色々お芝居を観て回った中で給与じゃないですけど、きちんと仕事に対して対価が支払われるようなところを探していた中の一つがク・ナウカ シアターカンパニーだったんです。
―執筆活動については演劇をはじめられた頃から興味があったんですか?
佐々木 そうなんです。結局「言葉」っていうのに連動して。結果的になんですけど、僕が入団させて頂いたのが古典演劇を中心に活動している劇団だったので、必然的に「他人の言葉を自分の身体を通して言う」みたいな環境だった。読む追体験と身体を通して喋る体験というのとは体験レベルが全然違うと思うので、自分の言葉との対比みたいなものとしてそれが結果的にはよく合っていたというか。
詩みたいなことを殴り書きしていたんですよ。それがどんどんどんどん形作られていくことに、昔の人が考えたこととか世界だとかの影響が僕の中にも凄くありましたね。
―実際に身体を通して喋るとなると、古典の言葉は現代の言い回しとは違うので、少し言いにくい部分があると思うのですが。
佐々木 若い頃はバカだから「難しいことを言えている自分がなんかちょっとカッコいい」みたいな(笑)。でも理解は出来ていないし、まず発語が出来ない。普通に日常で会話をするのに選ばれていかない言葉ばかりが目の前に並んでいて、それを実際に口にするということ自体が俳優としてはもの凄く負荷がかかるので、それを成立させるということを突き詰めていくと必然的に俳優としての技量が上がっちゃうっていうか。滑舌が良くならなきゃいけないとか(笑)。
5、6年前は本当に会話劇が盛んで、現代口語劇が凄く勢いのあった時期だったので、逆行していましたけどね。選んだ道としては。
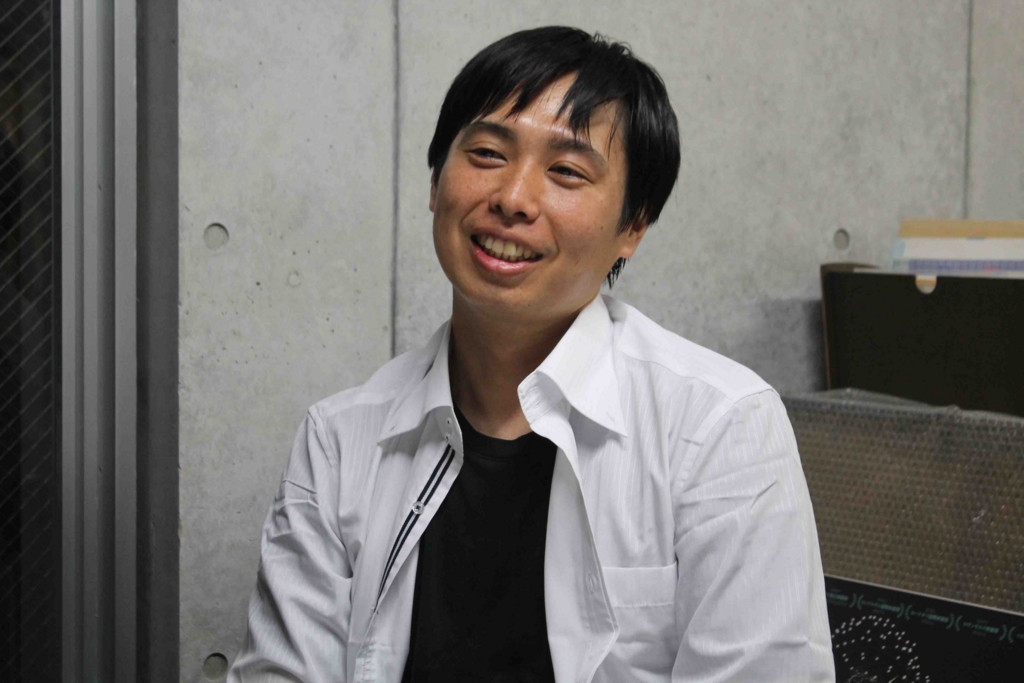
―その後に青年団の演出部に入られていますよね。
佐々木 本当は青年団のお芝居というか演技態も含めて、演劇の常識が全部ひっくり返る感じが凄く心地良くて、元々憧れていたんですよ。本当に好きで(笑)、好き過ぎて、そっちを選ばなかった。
―青年団はいわゆる現代口語演劇で、真逆ですよね。
佐々木 真逆ですね。だから当時から支離滅裂(笑)。後から平田オリザさんと宮城聰さんの仲が良いというのは後から知ったのですが「そうか、全然違うことをやっているけど、何か通ずるものがあるのかなぁ」なんて、ことあるごとに考えますね。その二人の作品の作り方とかアプローチとか演劇観とか。
―実際「通ずるな」というところはありますか。
佐々木 何でしょうね…二人とも背が小さい(笑)。真面目に言うと、視点というかビジョンが基本的に日本国内にない。当時のオリザさんはそうじゃなかったかもしれないですけど、宮城さんはもう明確にヨーロッパで闘うというのがビジョンとしてはっきりあって、平田オリザさんは恐らく自分の言葉を突き詰めていったら世界でも類を見ないものだった、っていうので、結果的にミニマルなものとマクロなものと全然真逆に行ったけど同じとこで会った、みたいな。そんな感じがする。
―佐々木さんのソロユニットである「リクウズルーム」は青年団にいる時に発足されたんですか?
佐々木 いや、その前です。青年団にいる時も活動していました。
―素朴な疑問なんですけど「リクウ」って何ですか?
佐々木 父方の祖父が俳人で、その俳号が「六宇」(りくう)なんですよ。当時は社会派な俳句を詠っていたらしく、著書が残っているので読んだら全然分からない(笑)。父が小学校一年生くらいの時に亡くなっていて、僕自体は祖父と面識がないので話しか聞いていなかった。それで、俳優として活動する時に別の名前を付けようと思って父に話をしてみたら「うちのじいさんがこんなことやってるんやで〜」みたいな感じのことを言うので(笑)、「凄く素敵な名前だね」という話で、それを拝借して。
劇団を退団する時に本名に戻そうということで本名に戻して、自分で何かをやる時に「リクウ」を使って活動してみようかな、と。
―「リクウズルーム」って音だけ聞くと「リクウの部屋」という意味かなと思うのですが、アルファベット表記の時は「reqoo-zoo-room」と書かれていますよね。
佐々木 あれはただの言葉遊びですね(笑)。でもそういう概念はちょっとあるかもしれないですね。こんな言い方はあれですけど、見世物小屋というか、動物園。動物園という考え方が好きなんですよ。あれが世界の縮図のように見えるので、「リクウズルーム」自体がプラットフォーム、ネットワークじゃないですけど、そういうものを思い描いてやってみようかなぁという風には当時は思っていましたね。
―そのネットワークというところと、ソロで活動されているということは関係があるんでしょうか。劇団員を持つのではなくて、そういうプラットフォームとしてある、というか。
佐々木 そうですね。これは凄くネガティブですけど、劇団にいた人間として劇団をやることの大変さは負えないなぁと思って。劇団を運営されている方は総じて凄いなと思います。経済的な面もそうですし、人様の時間を預かるわけなので「そんな器じゃないかなぁ」と思って。一人の方が気楽だなっていうのがあってやっていましたけど(笑)。
―青年団に入る前から「リクウズルーム」をやられていたとのことでしたが、青年団の演出部に入られて影響を受けた部分などはありますか?
佐々木 それは「場所」と「人」ですかね。青年団は「場所」があって「人」がいる。当時は自分が「リクウズルーム」を立ち上げたことで制作面というか運営面を勉強しようと思って門戸を叩いたんですよ(笑)。どういう作品を作っていてどういう活動をしているのかということは重々分かっていたので、中のソフト面がどうなっているのかというのがちょっと知りたくて。
―やっぱり「会計演劇」というシリーズをやられたのも、劇団の厳しさみたいなものに触れたから、ということなんでしょうか?
佐々木 それは全く発想が違って、リクウズルームは専属俳優は持たないのですが、会計担当者と、デザインや技術を担当する人間と、アートマネージャーの3人と僕とでチームになっているんですよ。会計を担当しているのが、普段池袋のあうるすぽっとや六本木アートナイトで助成金を管理している五藤というのですが、彼と出会う以前に、僕も組織を運営する上で会計のことも勉強しなければいけないなと思って、ちょっと簿記を齧ってたんですよ。損益計算書とか貸借対照表があって、最終的に年間の収支で財務諸表を出すんですけど、費目と数字がダアーっと出ているんです。それを見ていて「何か演劇のテキストにならないかなぁ」とずっと思っていたんですよ。そうしたら、演劇の実演家じゃない側の、アートマネジメントの勉強をしていてかつ会計を本当にやって来た、その五藤が同じことを考えていたんですよ。“僕は財務諸表をパッと見るだけで「その会社が一年間どれだけ頑張って来たのか」「どれだけダメだったのか」ということがお話・物語に見えるんです”、と。なので、「一緒にやりませんか?」と。自分だけで何となくそれで実際にやってみようとしても専門性がないので粗くなってしまいますが、そういう部分で彼に助けてもらったり出来る。
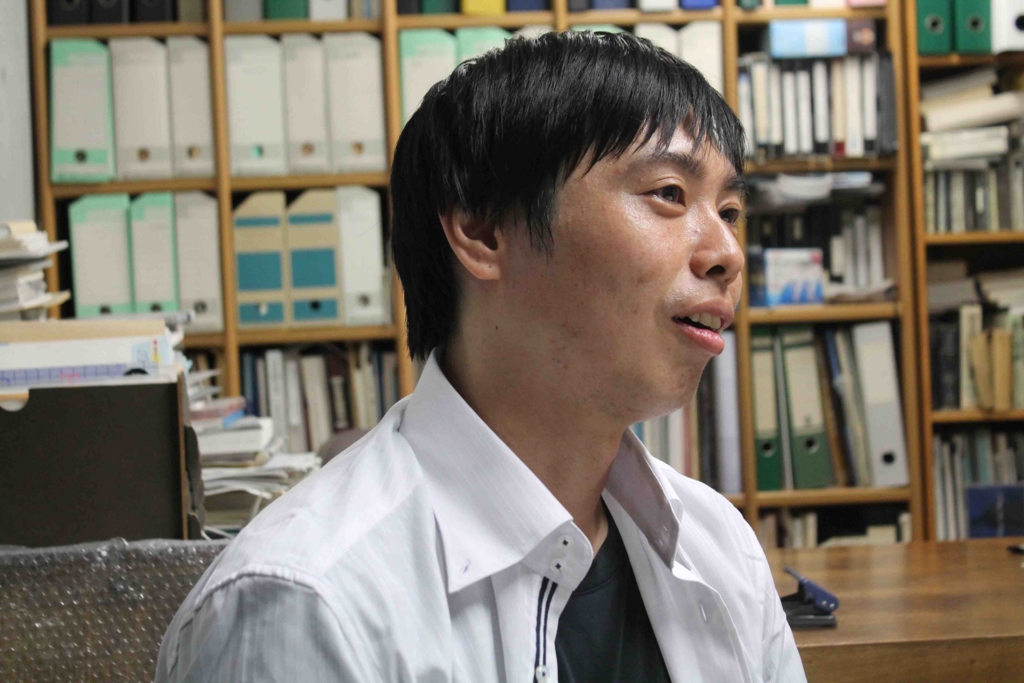
だから「会計で演劇をやりたい」というのは彼の企画なんですよ。僕の発信じゃなくて。さっきプラットフォームと言いましたけど、僕が必ずしも発案するのではなくて、チームの中で「こういうことやりたい」ということを「じゃあ僕がとりあえず形にしますね」という風にするという組織体系になっていて。
―「企画持ち込みOK」みたいな感じなんですね。
佐々木 全然OKです、本当に。
―コラボレーションもよくされていると思うんですけど、向こうから「こういったことがやりたい」と言われて実現することが多いんですか?
佐々木 今でこそ意識的にコラボレーションという風になったんですけど、元々はそれもたまたまで。2013年に東京都の事業でアジア舞台芸術祭というのをやっていて、その東京代表の演出家の一人として採択してもらった時に、コンテンポラリーダンスと一緒にやらなくちゃいけなくなったから(笑)、それが高じて、ですかね。あとは「文脈が通じない」こととやるということが面白かったんです。ストレスじゃなくて「分からないから仕方ないよね、じゃあどうやって分かるようにしていこうか」みたいなところから。
そうやってポジティブに見られるのは、きっと古典をやってきた部分があるから。古典ていうのは基本的に作家が死んでいるんで(笑)、「これが正しいです」という答えがない中から出発するんですよ。作家さんがいればその作家さんの絶対的なお答えがあるわけじゃないですか。大先生の「これはこういうつもりで書きました」とか、それを元にしていけるけど、それがないから演出家を含めて「これ、どうだろうね」というところからはじまるので、その辺に関してはストレスというよりかは自然だったな。
それがたまたま僕の場合は運良く上手いこと自分の中に嵌ったので、それが「会計」になったり色々なものになったり、ですね。「コラボって何か今、流行ってるよね」というのに乗っかっているわけじゃなくて、たまたまですよ。
―それでは今年5月に上演された『見えないスンマ』の話を。この作品にはアクターズ・コース第2期修了生の田中孝史さんが出演されていましたが、田中さんはどんな役者でしたか?
佐々木 孝史くんは…映画美学校のアクターズ・コースはやっぱり青年団との結びつきが強いので、演劇の種類として「会話」っていうものを凄く大事にしていて、「会話体」って言ったら変ですけど、そういう普通に話してダイアローグを積み上げていく、というようなことにこだわりがあったみたいで。それで彼と一回「例えば会話劇で活躍をしたいのだとしたら、今は発想を変えて「会話とは何か」ということを考えて、会話から離れるといいんじゃないかなぁ」ということを話したんですよ。演劇って一面的に会話だけではないし、例えば演説っていう側面もあればモノローグとか、色々あると思うんですよね。その中で会話というところだけに光を当て過ぎないで、例えば「会話しか喋ったことがない人が長いセリフを喋ったらどうなるのか」とか、そういうことに興味を持てるように「まず自分の可能性を見ましょうね」という話をして。それが彼にとっては良かったのか、そういう感性の開き方をしてから、彼は凄く楽しそうに生き生きと、もう全然別人みたいになっちゃってて。最初は窮屈そうに色々やっていたんですけど「やることは同じなんだよ」という話をして。
―確かに映画美学校では、平田オリザさんの講義などで「対話と会話の違い」みたいなお話をされます。
佐々木 「知らない人に対して喋るのが、対話」とかね(笑)。下世話だけど「会話劇業界(笑)で活躍したかったら会話劇じゃないことで活躍した方が会話劇業界が近づいてくるよ」ってな話をしたんだ(笑)。
―そうなんですか?(笑)
佐々木 だと思うよ。「誰が観ているか分からないから」っていう話をした。
―そういうお話をして、田中さんは楽になったんですね。
佐々木 楽になったと思います。「上手くやろう」と思っていて、自分が培って来たものが通用しないって分かって、誰しもそこから自分なりにあがかなきゃいけないというのは当然なんですけど「なんて声をかければ良いかな」と思っていた時に「別に今持っているもので良いんじゃないの」っていうところからはじまって。チャンネルの話だけですね。「今、孝史くんはこういうチャンネルだけで合わそうとしているから合わないだけで、みんな持っているけどそのチャンネルがあることに気付いていないだけだから、そういう意識を持っていけばすぐに出来るようになるよ」みたいな。
だから、多分そういうことは映画美学校のアクターズ・コースで色々な方がレッスンされていることと絶対にリンクすると思うので、基本的な理念とか考え方みたいなのは間違いなく備わっているから、それをどういう風に引き出してあげるか、というか、思い出させてあげるか、とか、そういうことなのかなぁと思って。
―修了公演について伺っていこうと思うのですが、今回は完全新作で書き下ろしていただけるんでしょうか?
佐々木 書き下ろします。
―今までも「会計演劇」とか「AR(拡張現実)」を取り入れたりだとか、色々と新しいことをされていたかと思うのですが、今回挑戦してみたいこととかやってみたいことはありますか?
佐々木 映画美学校なので「映画」ですよね(笑)。深田晃司さんと以前「映画の時間と演劇の時間と全然違いますよね」という事について話した事がありますが、それ並に違うのは「演技態」というか演技の仕方。カメラの前でやる演技と舞台上でやる演技っていうのは全然違うなぁと思うんですよね。その辺の差とかって、実際に演技をしている人は特に思うんじゃないかなぁと思っていて、そのことを考えつつ出来れば良いかなと思いますけど。やっている側は同じことをやっているつもりなんでしょうけど、やっぱり見え方が違いますよね。
―やはりカメラ前なのか観客の前なのかで「対象」が変わるので、それに合うようにチューニングしていくことで演技が異なるんでしょうか。
佐々木 その辺のことを考えてみたいな、というか。それは結局は「身体」がどういう状態か、良く言われる「身体性」というやつが、映像の演技と舞台の演技というところの落とし所だと思うので、「身体」をテーマに何か作っていければいいかなぁと思います。
―修了公演は俳優養成講座の最後のカリキュラムになるのですが、これから入る俳優養成講座生に「半年間、こんなことを学んで修了公演に臨んで下さい」ということはありますか?
佐々木 表現って地続きだと思うので、色々なものに触れていって欲しいですね。それは凄く思います。ちょうど今日もその話をしていたんですけど、例えばクラシック音楽の世界の人は、演劇に対する認識として、リスペクトがないことが多いと感じます。というか「演劇って何?」「オペラじゃないの?」みたいな。もちろん演劇を教わっていないから、そうなのは当然なんですけど、僕は単純に、例えば戯曲がオペラになっているという認識が日本人の中にそんなに浸透していないからじゃないかと思うんですよね。それは絵画でもあると思うんですよ。色々ないわゆる芸術・アートっていうものが互いにコラージュしたりだとか結びついたりだとか色々なことがあってそれぞれが補完されている。それを、完全に理解するということは多分無理だと思うから、触れるだけで良いと言うか、空気を吸うみたいな感じでも良いので、美術館に行ってみるとか文豪小説を読むとか、ちょっと気取ってほしいですかね(笑)。分からなくても良いというか、まずはファッションでもいいので。「(映画)美学校」といっているくらいですからね(笑)。

もちろん映画は特に気にして、関心があるので皆さんここに通うと思うのですが、一見関係なさそうだな、みたいなことが実は関係していたりだとかするので。それが行き過ぎると僕みたいに「会計」だとかアートですらないところにも行く(笑)。「電気」が気になるだとか「数式」が気になるとか、そういうところに行ければ、そういうところから結びついたら世界が広がるかなぁと。それだけでも豊かな人生を送れるんじゃないかなと思ったりしますけど(笑)。「これなんだろう!?」みたいな感じで。触れてみて「分かんないよね」みたいな感じだったら良いんですけど、食わず嫌いではなくてね。もちろん「文章を書いてみる」でも良いですしね。何でも良いと思うんですよね、「表現」と呼ばれるものであれば。まぁそんなこと言ったら人間、生きること自体が「表現」だから区分けする理由もないんですけど。そんなところですかね。
―受講を迷われている方にもメッセージがあればお願いします。
佐々木 もう絶対に来た方が良い(笑)。こんな渋谷の、本当に悪い意味じゃなくて、猥雑な場所にある学校なので。こういう「どうしたらいいんだ!?」みたいなところにライブハウスがあったりだとか、映画美学校やユーロスペースの入っている KINOHAUS というビルも当然そうだし、すぐ傍には文化村の劇場もあるし、ということを味わうだけでも凄く豊かになると思うので、是非この映画美学校に入ったら良い(笑)。来て下さい。お待ちしております。
******************************************************************************************************

佐々木透さん、ありがとうございました!